熊楠を物心両面から援助した人としては、横浜の平沼大三郎、神戸の小畔四郎、東京の上松蓊、田辺では毛利清雅、喜多幅武三郎らが挙げられる。いずれも熊楠が晩年にかけてもっとも頼みとした人びとである。平沼は母子ともども熊楠一家の生活のことに意を用い、小畔は調査の費用(たとえば第1回高野山調査行など)をかなりの部分で負担し、上松は熊楠の研究に必要な書籍、筆記具、顕微鏡などあらゆる要請を一手に引き受け、買い整えるといった協力ぶりである。
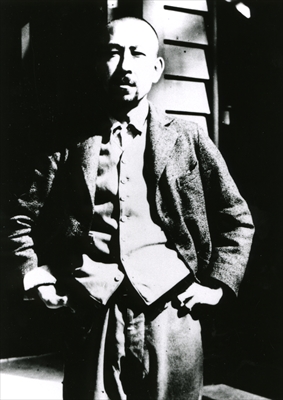
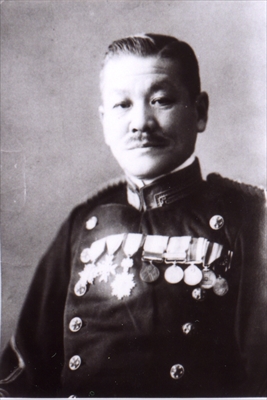

これに対して毛利は「牟婁新報」社主、後には「紀伊毎日新聞」社長といった言論人であり、県会議員としても発言力がある。熊楠の神社合祀反対運動に惜しみなく紙面を提供し、自らも同調して行動した。熊楠の逸話を彩る県議選選挙事務長就任話も、友人の毛利の劣勢をはね返すには何か奇手を編み出さなければと、川島友吉(草堂)らの献策で急に決まったことである。前回の選挙で毛利は落選、今度の選挙に期待がかかったのであるが下馬評がよくない。ためらう熊楠に、せめて2日か3日でもと川島は説き、熊楠も、いままでの友情と神島保存の今後を思うと、今度の県議選には毛利をぜひとも勝たせたい、そういう思惑も交錯しての承諾だった。推薦演説に熊楠が立つ、この噂はたちまち広がり、演説会場は近郊の人を含めて超満員。推薦の辞を代読する人のそばで熊楠はただ椅子に腰を掛けているだけだったという。作戦は図にあたって毛利は辛勝。神島の国の天然記念物化に、熊楠を助けて奔走した。

1941年12月29日に、熊楠は74歳の生涯を閉じた。亡くなる前日、床に着く際に、「天井に紫の花が一面に咲き実に気分が良い。頼むから今日は決して医師を呼ばないでおくれ。医師が来れば天井の花が消えてしまうから」と言い残したという。それから夜中に「野口、野口、文枝、文枝」と大声で叫んだ。野口利太郎は闘病生活を送る熊弥の面倒を見た人物で、2人の子供に対する思いを託した言葉であった。この言葉を聞き取った長女文枝は、亡くなるまで自分の名前を「熊弥」に代えて語り継いだ。
喜多幅は和歌山中学での同級生であるが、入学の2日前に出会った友として熊楠は他の同級生と区別して特に親しくしている。田辺に来住したのもその縁であり、熊楠一家の主治医として終生の交わりだった。喜多幅没後、暗夜の灯火を失いめっきり心弱くなった、と熊楠はいう。

熊楠の没後、妻の松枝、文枝、娘婿にあたる岡本清造らの手により、書庫に残された膨大な蔵書や資料は大切に保存された。和歌山、東京、アメリカ、キューバ、ロンドン、那智、そして田辺にいたる熊楠の無限の知的好奇心の跡を示す数万点の資料は、ほとんど当時のままで、未来の世代に継承されることになったのである。

岡本は日本大学経済学部教授でありながら南方家の一員として資料の整理・調査に努め、1947年にミナカタ・ソサエティの岡田桑三が南方家を訪れた際には一通りの説明ができるまでに調査を進めていた。また、1949年10月には日本大学六十周年記念祝典において、熊楠の資料を昭和天皇に天覧、ご説明をしている。






